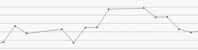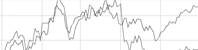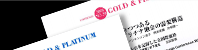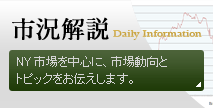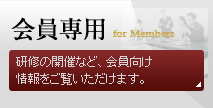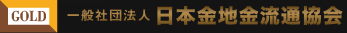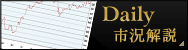2024年6月
石福金属興業株式会社 管理部資材グループ 北川 拓
- 金市場の動向
- プラチナ市場の動向
- 為替市場の動向
金市場の動向 6月の動き

ドル建て金相場
2337.70ドルでスタートしたロンドン金相場は、3日発表の5月米サプライ協会(ISM)製造業購買担当者景況指数の悪化を受け米連邦準備制度理事会(FRB)による年内の利下げが強く意識され、6日に月間最高値の2360.60ドルまで上昇した。しかし7日発表の5月米雇用統計は市場予測を大きく上回り、米国の早期利下げ観測が後退すると急落に転じ10日には2300ドル付近まで下落した。
急落への反動と、5月米消費者物価指数(CPI)の軟調な結果を受けた対ユーロでのドル安が進行し一時2330ドル近辺まで上昇するも、13日開催の米連邦公開市場委員会(FOMC)での金利の据え置き、パウエルFRB議長の利下げへの慎重姿勢が圧迫材料となり2310ドル台まで下落した。フランスのマクロン大統領による議会の解散・総選挙実施の宣言を受け欧州の政情を不安視する見方から反発する場面も見られたが、6月下旬にかけては2320ドルを挟んだレンジで推移した。
その後、20日発表の5月米住宅着工件数が市場予測を下回った事に加え、米フィラデルフィア連銀6月製造業景況指数が2ヵ月連続の悪化となると再び米国の早期利下げが意識され2350ドル台を回復するもこの水準は長くは続かず、翌21日発表の6月米製造業購買担当者景況指数(PMI)、サービス業PMIが相次ぎ市場予測を上回る堅調な結果を受け米早期利下げ観測が再び後退すると2330ドル近辺まで下落した。以降、同値付近で推移する中、25日に米FRB高官が早期の利下げに慎重な姿勢を示すと26日には節目の2300ドル台を割り込み月間最安値の2299.65ドルまで下落した。翌27日には1~3月期の米実質GDP確報値で個人消費が下方修正されると米長期金利の低下やドル安が進む中、買い戻しに支えられ2330ドル台まで値を戻しこの月の取引を終えた。
急落への反動と、5月米消費者物価指数(CPI)の軟調な結果を受けた対ユーロでのドル安が進行し一時2330ドル近辺まで上昇するも、13日開催の米連邦公開市場委員会(FOMC)での金利の据え置き、パウエルFRB議長の利下げへの慎重姿勢が圧迫材料となり2310ドル台まで下落した。フランスのマクロン大統領による議会の解散・総選挙実施の宣言を受け欧州の政情を不安視する見方から反発する場面も見られたが、6月下旬にかけては2320ドルを挟んだレンジで推移した。
その後、20日発表の5月米住宅着工件数が市場予測を下回った事に加え、米フィラデルフィア連銀6月製造業景況指数が2ヵ月連続の悪化となると再び米国の早期利下げが意識され2350ドル台を回復するもこの水準は長くは続かず、翌21日発表の6月米製造業購買担当者景況指数(PMI)、サービス業PMIが相次ぎ市場予測を上回る堅調な結果を受け米早期利下げ観測が再び後退すると2330ドル近辺まで下落した。以降、同値付近で推移する中、25日に米FRB高官が早期の利下げに慎重な姿勢を示すと26日には節目の2300ドル台を割り込み月間最安値の2299.65ドルまで下落した。翌27日には1~3月期の米実質GDP確報値で個人消費が下方修正されると米長期金利の低下やドル安が進む中、買い戻しに支えられ2330ドル台まで値を戻しこの月の取引を終えた。
今後の見通し
強弱入り混じる米国経済指標の発表が続く中、高金利環境が継続し圧迫される場面も見られるものの各国中銀による買い、中東やロシア情勢を始めとした地政学リスクへの懸念にサポートされながら概ね堅調に推移するものと考えられます。
プラチナ市場の動向 6月の動き

ドル建てプラチナ相場
月間最高値の1029ドルでスタートしたロンドンプラチナ相場は、3日発表の5月米サプライ協会(ISM)製造業購買担当者景況指数の悪化が嫌気され5日に節目の1000ドルを割り込むと、7日発表の5月米雇用統計の市場予測を大きく上回る結果を受けたドル高の進行から11日には960ドル付近まで下落した。その後、12日発表の5月米消費者物価指数(CPI)の軟調な結果を受けたドルの下落で一時反発。しかし、13日開催の米連邦公開市場委員会(FOMC)では7会合連続で金利据え置きが決定しドル高が進行すると割高感から売られ14日には月間最安値の949ドルまで下落した。
安値拾いに支えられ960ドル台近辺で推移する中、18日発表の5月米小売売上高は市場予測を下回る結果を示し、米国の早期利下げ観測が再燃。利下げへの期待感を追い風に米株式市場が最高値を更新すると株高、同じ白金族であるパラジウムの急騰に連れて上昇し、24日には1000ドル台を回復した。その後は一時利益確定の売りに押される場面もあったものの、月末にかけ1000ドル付近で推移しこの月の取引を終えた。
安値拾いに支えられ960ドル台近辺で推移する中、18日発表の5月米小売売上高は市場予測を下回る結果を示し、米国の早期利下げ観測が再燃。利下げへの期待感を追い風に米株式市場が最高値を更新すると株高、同じ白金族であるパラジウムの急騰に連れて上昇し、24日には1000ドル台を回復した。その後は一時利益確定の売りに押される場面もあったものの、月末にかけ1000ドル付近で推移しこの月の取引を終えた。
今後の見通し
900ドル台では買われ1000ドル近辺では売りに押される上値重い展開が続いているものの、白金系鉱山各社はPGMバスケット価格の下落から生産の合理化の動きもあり、需給のバランス次第では大幅な上昇を見せる局面も考えられます。
為替市場の動向 6月の動き

ドル円為替相場
157.18円でスタートした6月ドル円相場は、3日発表の5月米サプライ協会(ISM)製造業購買担当者景況指数が市場予測を下回り米長期金利が低下すると156円を割り込み、5日には日銀の国債購入減額報道を受けて155円台前半まで下落した。
しかし、7日発表の5月米雇用統計が市場予測を大きく上回る結果となるとこの流れは一転し157円台まで上昇した。その後、12日発表の5月米消費者物価指数(CPI)の軟調な結果を受け一時156円台まで下落。しかし、13日開催の米連邦公開市場委員会(FOMC)での7会合連続の金利据え置き、日銀金融政策決定会合では国債購入額減額決定も具体的な内容が無く緩和的な姿勢と捉えられるとドル買い円売りが進み14日には再び157円台を回復した。その後も日米金利差が意識されドルは上昇を続け、FRB高官の利下げに対し消極的と捉えられる発言で158円台を突破すると6月米製造業購買担当者景況指数(PMI)、サービス業PMIの相次ぐ堅調な結果を受けて21日には159円台まで上昇した。円安方向に進む流れは加速を続け、27日には約38年ぶりに160円台を超え月末28日にはFRB高官が追加利上げの可能性を完全に排除したわけではないとの考えを示すと月間最高値の161.07円をまで上昇しこの月の取引を終えた。
しかし、7日発表の5月米雇用統計が市場予測を大きく上回る結果となるとこの流れは一転し157円台まで上昇した。その後、12日発表の5月米消費者物価指数(CPI)の軟調な結果を受け一時156円台まで下落。しかし、13日開催の米連邦公開市場委員会(FOMC)での7会合連続の金利据え置き、日銀金融政策決定会合では国債購入額減額決定も具体的な内容が無く緩和的な姿勢と捉えられるとドル買い円売りが進み14日には再び157円台を回復した。その後も日米金利差が意識されドルは上昇を続け、FRB高官の利下げに対し消極的と捉えられる発言で158円台を突破すると6月米製造業購買担当者景況指数(PMI)、サービス業PMIの相次ぐ堅調な結果を受けて21日には159円台まで上昇した。円安方向に進む流れは加速を続け、27日には約38年ぶりに160円台を超え月末28日にはFRB高官が追加利上げの可能性を完全に排除したわけではないとの考えを示すと月間最高値の161.07円をまで上昇しこの月の取引を終えた。
今後の見通し
日銀は国債購入額減額を発表したものの方針の発表に留まった事に加え、米国の利下げ時期も不透明な事から円安基調が当面継続するものと考えられます。